舟を編む ― 2013年05月21日
釣りの映画だと思って見に行ったのですが、辞典の映画でした♪
勘違いしてみましたが、とても良い映画でした♪
そもそも、仕事だけで人生が終わってしまいそうなので、やりたいことで、できることは全部やろうと思って、月曜日のレディースディは映画に行こうと決めてみたのですが、たいして内容もチエックせずに、2本見ようとしたのです。
ですから、タイトルで決めるしかなかったのです。
怖い映画と、アクション映画ばパス!!
しかし・・・このタイトルは絶対釣りの映画だと思ってしまいますよね♪
そもそも、この映画に行ったのは、釣りに行き、ひさしぶりに昔行った海水浴場に行き、下田の友だちの実家のお父さんの話を思い出したからです♪
そのお父さんは、船大工でした。
それも、繊細な仕事をする人だったようです。
ところが、それでは食べて行けず、子どもたちのために、いつも自分のやりたくない仕事をしていたそうです。
それを見て、子どもたちは、どうして、そんなに嫌な仕事ばかりしていて、自分のやりたい仕事をしないのかと批判もしたようです♪
誰かを守るために、嫌なことを我慢してやる、お父さんの生き方に感動して、私はいつも嫌なことを我慢しなくては・・・と思うからです♪
そんな船大工さんの話かな・・・と思ったのは
辞書を作るはなしだったんですよ・・・・・・
最初にも書きましたが、本当に映画としては、面白かったですし、本当に良くできていて、勉強にもなったな!と思って大満足でした♪
それにしても、2本映画を見て、両方とも7番の部屋で、椅子がFの14(一番好きな席)というのも、なんだな・・・笑
★★★★
勘違いしてみましたが、とても良い映画でした♪
そもそも、仕事だけで人生が終わってしまいそうなので、やりたいことで、できることは全部やろうと思って、月曜日のレディースディは映画に行こうと決めてみたのですが、たいして内容もチエックせずに、2本見ようとしたのです。
ですから、タイトルで決めるしかなかったのです。
怖い映画と、アクション映画ばパス!!
しかし・・・このタイトルは絶対釣りの映画だと思ってしまいますよね♪
そもそも、この映画に行ったのは、釣りに行き、ひさしぶりに昔行った海水浴場に行き、下田の友だちの実家のお父さんの話を思い出したからです♪
そのお父さんは、船大工でした。
それも、繊細な仕事をする人だったようです。
ところが、それでは食べて行けず、子どもたちのために、いつも自分のやりたくない仕事をしていたそうです。
それを見て、子どもたちは、どうして、そんなに嫌な仕事ばかりしていて、自分のやりたい仕事をしないのかと批判もしたようです♪
誰かを守るために、嫌なことを我慢してやる、お父さんの生き方に感動して、私はいつも嫌なことを我慢しなくては・・・と思うからです♪
そんな船大工さんの話かな・・・と思ったのは
辞書を作るはなしだったんですよ・・・・・・
最初にも書きましたが、本当に映画としては、面白かったですし、本当に良くできていて、勉強にもなったな!と思って大満足でした♪
それにしても、2本映画を見て、両方とも7番の部屋で、椅子がFの14(一番好きな席)というのも、なんだな・・・笑
★★★★
コメント
_ ニンジャ乗り ― 2013年05月24日 00:01:12
_ yume ― 2013年05月24日 00:12:59
この本は、2012年本屋大賞で1位に選ばれている。本屋大賞は、「全国の書店員が選んだ、一番売りたい本」として毎年選考され、今年で8回目となる。2004年の第1回が「博士の愛した数式」(小川洋子著)で、昨年が「謎解きはディナーのあとで」(東川篤哉著)である。このコーナーでも、5回目の受賞作品「告白」(湊かなえ著)を2009年6月号に、翌年にも「天地明察」(沖方丁著)を紹介した。先日、アマゾンが2012年上期の和書総合ランキングを発表した。この総合分野には健康・ダイエット書籍も含まれているが、今回紹介の本は上位にあるのでベストセラーといえる。さて、著者について少し触れておきたい。就職試験で出版社を受験し、その文才を認められ採用される。会社勤めをしながら執筆活動を続け、2005年に「私が語りはじめた彼は」で山本周五郎賞の候補となり、翌年「まほろ駅前多田便利店」で直木賞を29歳で受賞している。80年近い直木賞の歴史で20代の女性受賞者は、平岩弓枝氏を入れて4人である。この本は若くて有望な作家の最新作である。
舟を編むとは(その1) ―― 舟は大海を漂うもの ――
この小説は、ファッション雑誌で2年間連載したものを書籍化している。連載当時から話題となっていた。ストーリィは、出版社の辞書編集部の新しい辞書「大渡海」を作る過程の編集部員の悩み、葛藤、喜びを描いたものである。辞書名の「大渡海」は、「言葉の海を渡る舟」であると言い、「もし辞書が無かったら、我々は茫漠とした大海原にたたずむほかない」と書いている。過去から現在に至るまで、辞書が果たす役割は、言葉の道標である。
舟を編むとは(その2) ―― 「編む」の歴史を探ってみる ――
「編む」を調べると、「①糸・竹・籐(とう)・針金・髪などを互い違いに組み合わせて、一つの形に作り上げる。②いろいろの文章を集めて書物を作る。編集する。③計画を組み立てる。編成する。」(大辞林)である。この「編む」の歴史は古く、日本では縄文時代から編物があり、衣類だけなく道具や敷物に広く使われていた。しかし編集の意味は中国語から来ているという。舟を編むという発想が、辞書編纂の膨大な作業を一言で表現している。
舟を編むとは(その3) ―― 編むものは何であったのか ――
この本は小説であるが、辞書編纂に関わる詳細なプロセスが書かれてある。数年前改訂された広辞苑は、24万語と3千の図版や地図が収録されている。この小説の中でも書かれてあるが、言葉の引用文(用例カード)の収集が150万枚近くあり、その言葉は年々変化している。この本の最後に「辞書の編集に終りはない。希望を乗せ、大海原をゆく舟の航路に果てはない」と結んでいる。辞書編纂は、人のロマンと情熱のドラマの様に見えてくる。
舟を編むとは(その1) ―― 舟は大海を漂うもの ――
この小説は、ファッション雑誌で2年間連載したものを書籍化している。連載当時から話題となっていた。ストーリィは、出版社の辞書編集部の新しい辞書「大渡海」を作る過程の編集部員の悩み、葛藤、喜びを描いたものである。辞書名の「大渡海」は、「言葉の海を渡る舟」であると言い、「もし辞書が無かったら、我々は茫漠とした大海原にたたずむほかない」と書いている。過去から現在に至るまで、辞書が果たす役割は、言葉の道標である。
舟を編むとは(その2) ―― 「編む」の歴史を探ってみる ――
「編む」を調べると、「①糸・竹・籐(とう)・針金・髪などを互い違いに組み合わせて、一つの形に作り上げる。②いろいろの文章を集めて書物を作る。編集する。③計画を組み立てる。編成する。」(大辞林)である。この「編む」の歴史は古く、日本では縄文時代から編物があり、衣類だけなく道具や敷物に広く使われていた。しかし編集の意味は中国語から来ているという。舟を編むという発想が、辞書編纂の膨大な作業を一言で表現している。
舟を編むとは(その3) ―― 編むものは何であったのか ――
この本は小説であるが、辞書編纂に関わる詳細なプロセスが書かれてある。数年前改訂された広辞苑は、24万語と3千の図版や地図が収録されている。この小説の中でも書かれてあるが、言葉の引用文(用例カード)の収集が150万枚近くあり、その言葉は年々変化している。この本の最後に「辞書の編集に終りはない。希望を乗せ、大海原をゆく舟の航路に果てはない」と結んでいる。辞書編纂は、人のロマンと情熱のドラマの様に見えてくる。
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。
トラックバック
このエントリのトラックバックURL: http://yumemoon.asablo.jp/blog/2013/05/21/6816935/tb
※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。
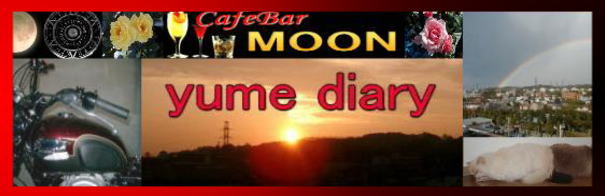



でも辞書の映画とは…
絶対に思わないですよ!